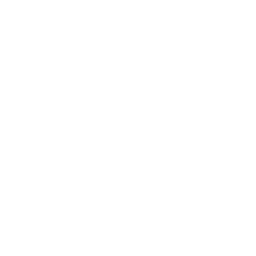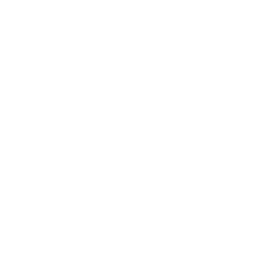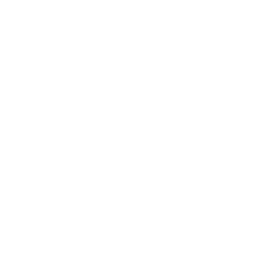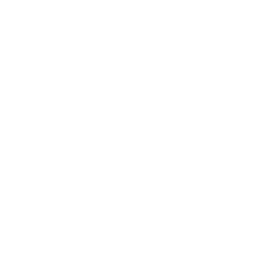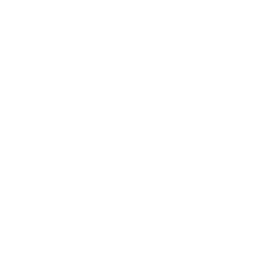7月7日小暑とは?🌸自然と暮らす12か月🌸今日は何の日
小暑(しょうしょ)と自然食の知恵
~発酵の力で、夏を元気に乗り切る季節の食養生~
二十四節気のひとつ「小暑(しょうしょ)」は、毎年7月7日頃。七夕と重なることも多く、日本の暦と季節のリズムを感じる節目でもあります。
この時期は、梅雨明けが近づき、空気がムッと重くなり始める頃。草木は力強く伸び、蝉の声が響き、空には入道雲。いよいよ“夏本番”が迫ってきます。

小暑の頃のめぐみの杜の菜園には、トマトや花おくらやきゅうりが実り始めました。いよいよ夏野菜の収穫が始まります。
そんな自然の変化に、私たちの身体も敏感に反応しています。暑さによる疲れ、湿気によるだるさ、胃腸の不調……。
だからこそ、小暑の頃には、自然のリズムに寄り添った食の工夫=自然食と発酵食の知恵がとても大切になってきます。
小暑とは?
「小暑」とは、「少し暑さが始まる頃」という意味。
一年のうちでもっとも湿気と気温の上昇が重なる季節のはじまりで、体にこたえる時期です。
古くからこの時期は、「暑中見舞い」を出し始める目安とされ、暑さが本格化する前の準備期間と考えられてきました。
また、「小暑」は単に気温の指標ではなく、農事暦でも重要な節目です。梅雨明けとともに稲の分けつが進み、農作業はさらに忙しくなっていく頃。私たちの暮らしもまた、この自然の営みと無関係ではありません。
小暑から大暑へ、そして土用へ
小暑から約半月後には「大暑(たいしょ)」を迎えます。これは一年でもっとも暑さが厳しくなる頃。
そしてその前後に「夏の土用」が始まります。
「土用」とは季節の変わり目の調整期間。五行思想では“土”の気が強くなる時期とされ、湿気が体内にたまりやすく、消化力や免疫力が落ちやすいと考えられてきました。
つまりこの小暑〜大暑〜土用の流れは、
「暑さの本番が来る前に、食事や生活で体を整える大切なタイミング」
ということになります。先人たちはこの時期を“夏に向けた仕度の時期”として、とても大切にしてきたのです。
小暑の頃の暮らしの知恵
この時期の体調不良には、以下のような特徴があります。
- 暑さによる寝苦しさ、寝不足
- 胃腸の疲れや食欲不振
- 湿気によるむくみ、だるさ
- 汗によるミネラルの消耗
こうした季節特有の悩みに対し、自然食や発酵の知恵はとても役立ちます。以下に、特におすすめの食材と調理法をご紹介します。
◆ 小暑におすすめの発酵食・自然食
▷ 梅干し
小暑の頃は、ちょうど「梅の土用干し」を始める時期。
梅干しに含まれるクエン酸は、疲労物質の分解を助け、体をシャキッと目覚めさせてくれます。
自家製の18%塩分の梅干しは、表面に乳酸菌が自然に生まれ、腸内環境を整えるお手伝いにも。
一粒の梅干しが、体を中から整える天然の“おくすり”になるのです。
▷ 甘酒(米麹から作るもの)
“飲む点滴”といわれる甘酒。暑さに弱った胃腸にやさしく、エネルギーと水分、ミネラル、酵素を同時に補ってくれます。冷やしても、常温でも、朝の1杯がおすすめです。
▷ 塩麹・醤油麹
発酵調味料は、食材を柔らかく消化しやすくし、少ない調味でも素材の旨味を引き出します。暑い日は、塩麹に漬けたキュウリやゴーヤなど、冷菜で「陰」を取り入れるのもおすすめ。
▷ ぬか漬け・味噌汁
乳酸菌たっぷりのぬか漬けは、腸を整え、水分代謝を助けてくれます。
また、発酵食品である味噌の味噌汁も、具に旬の夏野菜を加えることで、体の内と外をバランスよく冷やしてくれます。
◆ 調理の工夫で“熱を入れすぎない”
小暑の頃は、なるべく「重たすぎず」「冷たすぎず」、ほどよく加熱されたものをいただくことがポイントです。
- 重ね煮:野菜の陰陽を活かして重ねることで、火を通しながらもエネルギーを整える。
- 50度洗い:野菜を50度のお湯で洗うことで、酵素を活性化させ、うま味も引き出せます。
- 蒸し調理:炒めものよりも、蒸し料理で素材の水分と栄養を逃さずやさしく加熱。
これらは、暑い時期の身体にもやさしく、消化に負担がかからず、食欲が落ちている時でも自然に口に運べる調理法です。

めぐみの杜にて、7月7日11周年記念ランチ
小暑に寄り添う暮らしとは
小暑は、暑さの序章ではあるけれど、これからの夏をどう過ごすかの“鍵”になる時期です。
昔の人たちは、ただ暑さを避けるのではなく、自然の恵みを活かしながら、体と心を整える知恵を持っていました。
- 打ち水、風鈴、簾(すだれ)など「五感で涼をとる工夫」
- 旬の食材と発酵の力を借りた「夏を乗り切るごはん」
- 昼間の休息と、早寝早起きで「自律神経を整える暮らし」
こうしたささやかな工夫の積み重ねが、体にやさしい夏をつくっていくのです。
まとめ|小暑を“食”で乗り越える、やさしい夏の始まり
小暑は、自然の変化に呼応して、私たちの身体や暮らしのあり方も整えていく節目。
発酵の力や自然食の知恵を取り入れて、
“暑さに耐える”のではなく、
“暑さに寄り添う”暮らし方へとシフトしてみませんか?
季節の恵みを美味しくいただきながら、心と体を整える。
そんなやさしい夏のはじまりが、きっと心地よい日々を連れてきてくれるはずです。
自然の恵みに感謝して~