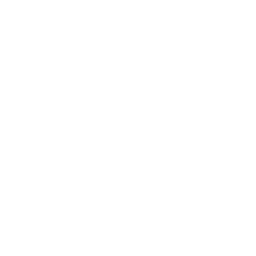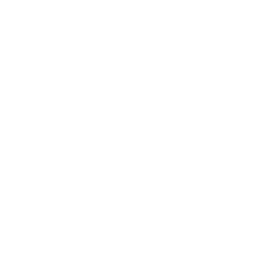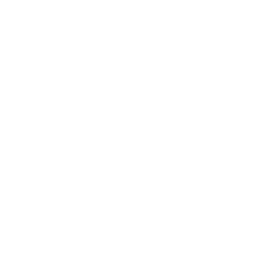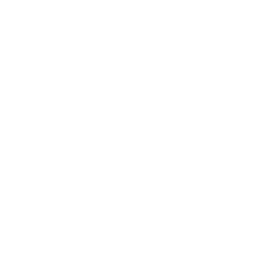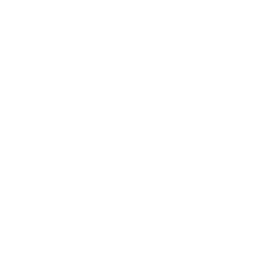8月7日立秋とは?🌸自然と暮らす12か月🌸今日は何の日
暦のうえでは秋。でも体感は真夏。
立秋に寄せて、自然と体の声に耳をすませる
今年は、8月7日より「立秋(りっしゅう)」の節気に入りました。
立秋は、二十四節気のひとつで、暦のうえではこの日から「秋」が始まります。
でも実際には、連日の猛暑。
セミが元気よく鳴き、冷たい飲み物が手放せず、エアコンはフル稼働。
「とても秋とは思えない」──というのが正直な感覚ではないでしょうか。
それでも、自然の小さな変化に気づいてみると、
たしかに「秋の入り口」は、もうすぐそこまで来ているのです。
暑中見舞いと残暑見舞いの違いとは?
日本には、季節のご挨拶として「暑中見舞い」と「残暑見舞い」があります。
- 暑中見舞い:梅雨明け~立秋前まで(7月中旬〜8月6日頃)
- 残暑見舞い:立秋(8月7日頃)以降、暑さが残る時期に(8月末頃まで)
「え?まだ真夏なのに“残暑”って?」と不思議に感じるかもしれません。
でもこの区切りは、「体感」ではなく「暦(こよみ)」のうえでの季節の変わり目です。
つまり、「立秋を過ぎたら“秋”」というのが、日本の伝統的な季節の見方なのです。
立秋を過ぎると、こんな自然の変化が
たしかに昼間は厳しい暑さが続きます。
でも、朝夕の風が少しやわらかく感じたり、
草むらから「リーン、リーン…」と秋の虫の声が聞こえてくることがあります。
立秋を過ぎると姿を見せ始める虫や自然現象にはこんなものがあります:
虫の音に秋を感じる♬
- アオマツムシ(リーンリーン)
- クツワムシ(ガチャガチャ)
- スズムシ(リーン…)
- コオロギ類(チンチロリン)
彼らは、夏のセミとは違い、どこか涼しげで、心に沁み入る音色を奏でます。
空を舞う秋の訪問者
- **赤とんぼ(アキアカネ)**が高い空を群れ飛びはじめます。
- ススキやオミナエシなど、秋の野草が少しずつ顔を出します。
- 雲の形も、夏の入道雲から、秋らしいうろこ雲やいわし雲へ変わっていきます。
立秋は、私たちの体も「秋支度」を始める時
この時期は、夏の疲れ(=暑さによる消耗)が出てきやすく、
それに気づかないまま無理をすると、体調を崩しがちです。
立秋ごろの体調変化
- 食欲が落ちる
- 寝つきが悪くなる
- 胃腸が冷えて調子を崩す
- 倦怠感やだるさ
- 汗のかきすぎによるミネラル不足
体はまだ「夏の暑さ」と向き合っていますが、
自然は少しずつ「秋」へ向かっている。
そのズレに気づいて、養生の意識を少し変えていくことが大切です。
立秋からのおすすめ食養生
温かい汁物を
冷房で内臓が冷えている人には、ぬるめのお味噌汁や重ね煮のスープが最適。
味噌や梅干しなど発酵食品で、腸内環境も整えていきましょう。
梅・しそ・らっきょう・黒大蒜
- 梅干しはクエン酸で疲労回復+殺菌効果
- 赤しそジュースはミネラル補給とリフレッシュに
- らっきょうの硫化アリルは、消化促進と夏バテ防止に
- 黒大蒜(くろにんにく)は、自然な甘味とともに疲労回復・抗酸化作用が期待され、夏の疲れをやさしく癒してくれます。

長岡式酵素玄米でエネルギー補給
胃に負担をかけず、体にしっかり届くエネルギーを。
優しい甘さで、自律神経も整います。

「体感の夏」「暦の秋」
いまは確かに「真夏の暑さ」。
でも、季節の暦では「秋の入り口」。
このギャップに気づき、無理なく橋渡ししていくことが、
健やかな秋を迎える準備になります。
自然を感じる心、食卓から整える知恵。
昔ながらの感覚を大切にしながら、
今という季節を心豊かに味わっていきたいですね。
自然の恵みに感謝して~