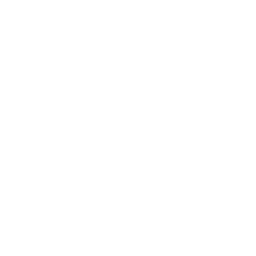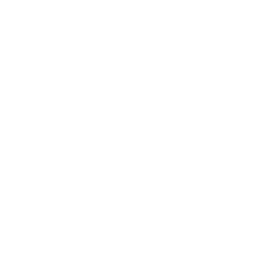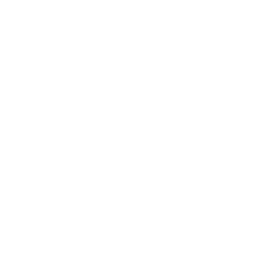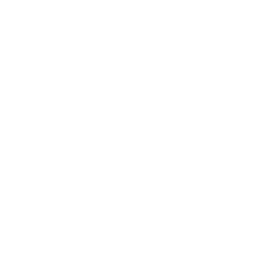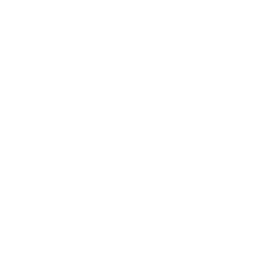土用とは🌸自然と暮らす12か月🌸今日は何の日
2025年の夏土用は、7月19日から8月6日まで。
「土用の丑の日」として耳にしたことがある方も多いと思いますが、
実はこの“土用”、とても奥が深く、季節の変わり目を健やかに過ごすための大切なヒントが詰まっているのです。
この記事では、そもそも土用とは何か?
そして、夏土用をどのように過ごすと良いのか?土用の丑の日に鰻を食べる?について、わかりやすくご紹介していきます。
土用の過ごし方
~季節の変わり目に、心と体を整える知恵~
「土用(どよう)」とは、立春・立夏・立秋・立冬の直前、約18日間の期間を指します。特に「夏の土用」は有名ですが、実は年に4回訪れ、いずれも季節が切り替わる大切な“調整期間”とされてきました。
古来、東洋の自然哲学「陰陽五行」では、春=木・夏=火・秋=金・冬=水に対応し、その間をつなぐ“土”のエネルギーを「土用」として位置づけ、体と環境のバランスを整える時期と考えられてきました。
■ なぜ土用が大切なのか?
季節が移り変わる時期は、気候・気圧・湿度の変化が激しく、心身も不安定になりやすい時期。
現代でも、「なんとなくだるい」「胃腸が弱る」「気持ちが落ち込みやすい」といった“未病”のサインが現れやすくなります。
だからこそ、土用は「無理をせず、余分なものを手放し、エネルギーを蓄える」ことが大切です。
■ 土用の過ごし方のポイント
1. 消化の良い、あたたかい食事を意識する
この時期は胃腸が疲れやすいため、重たい食事や冷たい飲み物は避け、煮物・汁物・発酵食品などを取り入れたシンプルな食事を心がけましょう。
- おすすめ食材:かぼちゃ・人参・さつまいも・れんこんなどの土の中で育つ野菜
- 発酵食品:味噌・醤油・ぬか漬け・梅干しなど
- 消化を助ける:生姜・山椒・大葉・みょうがなどの香味野菜
2. “気”を整える生活を意識する
無理なスケジュールは避けて、ゆっくりと呼吸する、深く眠る、温める。これだけでも気の巡りは変わります。
- 朝の散歩や軽いストレッチ
- 湯船にゆっくり浸かる(38〜40℃)
- スマホ・テレビ・SNSを一時オフにして「静けさ」を取り戻す
3. 感情のデトックスをする
土用は“内省”の時。感情が揺れやすい時期でもあります。湧いてくる感情を抑え込まず、やさしく見つめましょう。
- 日記や手紙で気持ちを言葉にする
- 深呼吸をして「今ここ」に意識を戻す
- 自然の中で過ごす時間をつくる
4. 土用の虫干し
クーラーや除湿機がなかった時代、自然の風と太陽の力を借りて、着物や掛け軸、書籍、楽器などを手入れする「土用干し(どようぼし)」が、年中行事の一つでした。
現代でも、暑くて乾燥しやすいこの時期は、カビや虫を防ぐために、着物や本を風に当てておくのにぴったりのタイミングです。
ふだん後回しになりがちなタンスの整理や、おうちの中の見直しにもいい機会。着物や本だけじゃなく、暮らしや心の中もちょっとスッキリ整えてみませんか?
引き出しや押し入れに風を通すように、心にもそよ風を通してみましょう。
5. 梅の土用干し
今年の6月に塩漬けして、赤紫蘇をもみ込んでおいた梅干し。

いよいよ夏の土用期間に「土用干し」をします。
土用干しとは、梅をお日様に当てて天日干しする、昔ながらの保存の知恵。
手間はかかりますが、実がぎゅっと締まり、香りもよくなり、保存性もアップします。
【昔ながらの土用干しの手順】
① 土用期間中、晴れが3日続く日を選びます。
朝のうちに梅をざるや干しかごに広げて、朝日が当たる風通しのよい場所へ。
夕方には取り込み、夜は室内で保管。
※赤紫蘇や梅酢も一緒に日に当ててOKです。


② この作業を3日間繰り返します。
③ 3日目の夜は取り込まず、外に出したまま夜露に当てて翌朝取り入れます。
夜露に濡れることで皮がやわらかくなり、しっとりとした梅干しに。

④ 干し終えた梅は、そのまま保存してもよし、梅酢に戻して柔らかく仕上げてもよし。
食感や味の好みに合わせて楽しめます。
私の場合は、干した梅をすぐには食べず、1年ほど寝かせてからいただくようにしています。
じっくり熟成された梅干しは、まろやかでコクのある味わいに育ちます。
なお、今年の梅干しは9月末ごろからが食べごろです。
【忙しい方へ:簡易版「土用干し」の方法】
「3日間干すなんて難しい…」
「日中は家にいないし、梅を出しっぱなしにできない」
そんな方には、こんな方法もあります。
◎ 瓶のまま天日に当てる
- 漬けたままの瓶(ガラス瓶)を、ふたを緩めにしてベランダや窓辺に出し、日光に当てるだけ。
- 1日30分〜1時間でもOK。数日間続ければ、ほどよく発酵が進み、香りも立ちます。
◎ 1日だけ干す「プチ土用干し」
- 晴れた日に1日だけざるに広げて干すだけでも、十分に風味が増します。
◎ 干さずに熟成させる
- どうしても干せない場合は、赤紫蘇と梅酢に浸けたまま冷暗所でじっくり熟成させるだけでも、自然な発酵で美味しく仕上がります。
土用干しは、できる範囲で、無理なく取り入れることが大切です。
梅と向き合う時間も、季節の恵みを感じるひととき。
どうぞそれぞれの暮らしに合った方法で、梅しごとを楽しんでくださいね。
■ なぜ土用の丑の日に鰻を食べるの?
2025年夏の土用の丑の日はいつ?
:7月19日(土)、7月31日(木)
年により1~2回ありますが、2025年は二の丑まである年です。
① 平賀源内による“マーケティング説”(もっとも有名)
江戸時代、夏場に鰻が売れずに困っていた鰻屋が、学者であり発明家でもあった平賀源内(ひらが げんない)に相談。
源内は、「“本日丑の日”と書いて貼り紙を出しなさい」とアドバイスしました。
当時、「丑の日に“う”のつくものを食べると夏バテしない」という風習があったため、
それが人々の関心を集め、鰻が売れるようになった――というのが通説です。
👉 この話は、「現代の広告の始まり」としても知られています。
② 丑の日に「う」のつく食べ物を食べるとよいという民間信仰
古来より、丑の日には「うのつくもの」(うどん、梅干し、瓜など)を食べると夏負けしないという言い伝えがありました。
鰻もそのひとつで、“う”のつく栄養価の高い食べ物として親しまれたと考えられます。
③ 鰻は滋養強壮に優れた食材だったから
- ビタミンA・B群、D、E、カルシウム、EPA、DHAなどを多く含み、
- 夏バテや食欲不振、疲労回復にぴったりの栄養源。
山上憶良(やまのうえのおくら)による、鰻(うなぎ)を食べることを勧める和歌が、『万葉集』巻十六に収録されています。
原文:『石麻呂に 吾れ物申す 夏痩せに 良しといふものぞ 鰻取り食(め)せ』
現代語訳:石麻呂よ、ちょっと言っておくぞ。夏痩せにはうなぎが良いと聞く。だから、うなぎを捕って食べなさい。
解説:この歌は、山上憶良が知人の石麻呂(いしまろ)に向けて詠んだもので、
「夏に痩せ細っているようだから、滋養のある鰻を食べて元気になりなさい」と、体調を気づかう思いやりの気持ちが込められているようです。鰻は奈良時代から「夏バテ対策の食べ物」として知られていたということですね。
暑さで弱りがちな体を元気にしてくれるため、鰻は土用の養生食として理にかなっていたのです。
とはいえ…
実は私自身、胃腸があまり強くなく、夏の暑い時期に鰻のような脂の多い食材を食べると、消化不良を起こしてしまうことがあります。
せっかくの栄養源ですが、体が受けつけないのでは本末転倒。残念ながら、私は鰻をいただくことができません。
その代わりに、夏バテ予防として私が日々取り入れているのが、らっきょう・梅干し・黒にんにく(黒大蒜)です。
- らっきょうは、胃腸を温め、消化を助ける働きがあり、シャキッとした歯ごたえも食欲を刺激してくれます。
- 梅干しは、クエン酸が疲労回復をサポートしてくれる日本のスーパーフード。
- 黒にんにくは、生のにんにくよりもマイルドで、体力を内側からじわっと支えてくれる感覚があります。
どれも自然の力を活かした、からだにやさしい食養生の知恵。
自分の体に合うものを選んで、無理せず、心地よく、夏を乗り越えていけたらいいですね。

■ 土用に避けたいこと(特に体調を崩しやすい方・敏感な方は意識を)
① 土を掘り起こす作業(土用=「土」の気が乱れる時期)
- 庭仕事や畑の耕作、井戸掘り、建築工事、地鎮祭など
- 特に「地面を動かす」行為は、土の神様(※土公神)を刺激するとして避けられてきました。
👉やむを得ず行う場合は、**間日(まび)**に行うとよいとされています。
※2025年夏土用の間日は:7月22日・23日・27日・28日・8月1日・2日
② 引っ越し・転職・結婚・開業などの「大きな決断・変化」
- 土用は不安定なエネルギーが流れやすい時期。
- 新しいことを始めるのではなく、内省・準備・メンテナンスに適した期間と考えましょう。
③ 無理な旅行や遠出
- 体調が不安定になりやすい時期です。
- 長距離移動やハードスケジュールは控えめにし、ゆったりと過ごすことを意識しましょう。
④ 暴飲暴食・冷たいものの摂りすぎ
- 夏土用では、暑さで食欲が落ちがちですが、冷たい飲食物は胃腸の働きをさらに弱めます。
- 消化器系(=「土」の臓器)にやさしい、あたたかくて軽い食事が◎。
⑤ 過労・徹夜・無理なスケジュール
- 「がんばりすぎ」は禁物。
- この時期は“立ち止まり、整える”ことが大事。
- 睡眠と休息をしっかり取ることで、次の季節に向けての体調が整います。
■ 土用の養生は、1年を健やかに過ごす土台づくり
土用は、ただ「うなぎを食べる日」ではなく、本来は、体と心を整えるチャンスの期間。
静かに、ていねいに、暮らしを見直すとき。
土のエネルギーが強まるこの時期に、しっかりと根を張るように自分を整えることで、次の季節も元気に迎えることができるのです。
どうぞ皆さまも、ご自身の心と体の声に耳を傾けながら、土用の18日間をていねいにお過ごしください。
自然の恵みに感謝して~